- HOME
- 本プログラムについて
- ターゲットタンパク研究「医学・薬学等への貢献」分野
- 自然免疫における病原体認識
自然免疫システムにおける病原体認識に関わる分子群の構造解析
代表機関:大阪大学免疫学フロンティア研究センター
代表研究者:審良静男(H19〜H21)、石井 健(H22)
2010年版パンフレット(背景と成果)の該当ページはこちら
自然免疫が注目を集め、ここ10年、研究が急速に進んできました。獲得免疫の前段階である自然免疫も、私たちヒトをはじめとする高等動物において生体の防御システムを担っていることが理解されるようになり、かつては免疫システムに非自己として認識されることはないと考えられていた核酸(DNA、RNA)が、自然免疫を引き起こすことが明らかになりました。研究がさらに進めば、将来有用な核酸ワクチンができるほか、核酸による自然免疫反応をうまく制御することによってアレルギー疾患やリウマチなどの自己免疫疾患を治療できるのではないかと、医療に生かす期待が膨らんでいます。
それでは核酸はどのようなしくみで自然免疫を引き起こすのでしょうか。入り口になっているのはおもに「Toll 様(トールよう)受容体(TLR)」と呼ばれるセンサーです。ヒトでは10種類のTLRが知られていて、このうち核酸に対応するのはTLR9など数種類です。どのセンサーがキャッチするのかは、相手がDNAかRNAか、二重鎖か一重鎖か、右巻きか左巻きかなど、核酸の構造によって決まっています。非自己である病原体の核酸、また自分由来でも傷ついたり壊れたりした核酸があると、これらのセンサーがキャッチして細胞内に信号を伝え、インターフェロンやサイトカインがつくられます。このような大阪大学微生物病研究所の石井 健准教授(当課題の分担研究者)らとの共同研究成果によって核酸が免疫反応を起こすしくみがだんだん明らかになってきました。
最近注目されているのは、特定の6塩基からなる配列を含む「CpGDNA」とよばれるDNAです。TLR9にキャッチされて、マウスにおいて抗がん、抗アレルギー、耐感染症などの作用を発揮することが明らかになりました。ヒト型もつくられて、臨床効果が調べられています。
私たちがぜひ明らかにしたいのは、TLR9がどのようにDNAを認識するか、その詳しいしくみです。そのためには、TLR9やDNAと結合したTLR9の構造を知ることが不可欠です。分担研究者である大阪大学蛋白質研究所の中川敦史教授のグループとの共同研究によりこれらの結晶化にも成功しているので、今回の研究においてX線解析で構造を解明し、今後の展開の基盤をつくりたいと考えています。
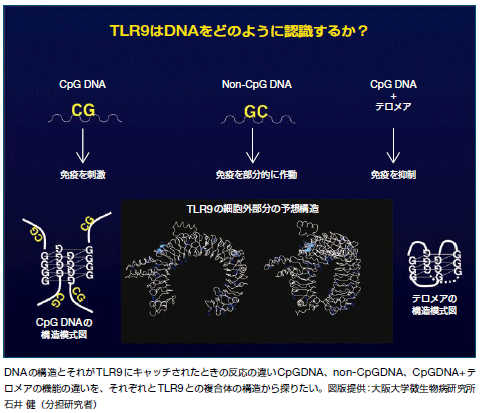

 サイト内検索
サイト内検索





